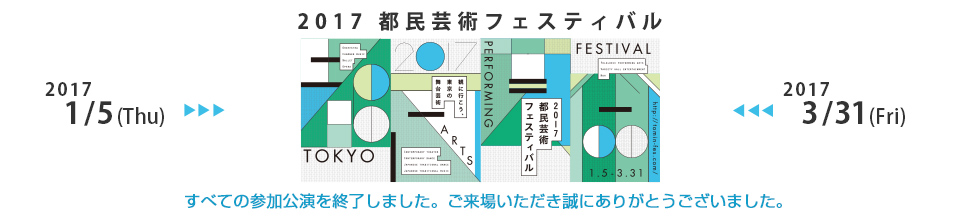2017都民芸術フェスティバル 公式サイト
伝統とともに現代を切りひらく

宝生 和英(ほうしょう かずふさ)さん
宝生 和英(ほうしょう かずふさ)
宝生流第二十世宗家。演能会「和の会」主宰。
1986年、室町時代より続く能楽の名門、宝生家に生まれる。2008年、東京藝術大学邦楽科卒業後、同年4月に宗家を継承。伝統的な演出に重きを置くほか、異流共演多数出演や復曲なども行う。また、現代に能楽の価値を生み出すため、能楽師としてだけではなくマネジメント・経営業務も行う。平成28年度文化庁文化交流使(東アジア文化交流使)に任命され、香港・イタリアをはじめとした海外文化活動にも力を入れている。
主な公演に、宝生会定例能・金沢宝生会・富山宝生会・名古屋宝生会・大阪七宝会・九州宝生会・山形庄内能楽堂・静岡新潟能楽公演・靖国神社夜桜能はじめ各地薪能のほか鹿児島国民文化祭(2015)、ミラノ万博(2015)、第21回ミラノトリエンナーレ万博(2016)、日伊国交樹立150周年事業ジャパン・オルフェオ(2016)など。
今回、宝生流宗家である和英さんは4年ぶりに「式能」の『翁』で翁役を演じられます。4年前と現在でお気持ちの変化はありますか。
前回演じた時は20代でしたが、今回は31歳になっています。年齢ごとに目指すべき舞台というのは変わってきますから、この4年間やってきた形が出るのではないかと思います。過去を意識したり振り返ったりしてもそこに答えはないので、今の時点でできることをやろうという姿勢ですね。
『翁』とは、どのような曲目※なのでしょう。
もとは人にフォーカスした芸術ではなく農業に関連したもので、「闇」や「死」といったネガティブな不安を取り除く作業としても行われていたものなので、僕自身は能楽以上に古い歴史があるものだと考えています。さらに、多宗教であった日本という国家が人々をつなげるために文化を使ったという1つの名残であり、日本の縮図のような曲だと思っています。流儀によって型は異なりますが、いずれもストーリーがあるわけではないので、ご覧になる方には「日本人のDNAを感じる」という意識で観ていただければいいかと思います。だからといって、日本人でなければ理解できない曲というわけではありません。もともと真っ白だった衣装が途中から現在の蜀江(しょっこう)模様に変わったのは、ビザンティンの影響を受けたとも言われていますし、翁の半分切れているような面は東欧でも見られ、謡の中にサンスクリット語が入っているというような逸話もあります。ですから『翁』は意外に世界共通の芸術性がある、グローバルな意識が強い曲目なのかもしれません。
式能とはどのような能楽公演なのでしょうか。
式能は「五番立て」※といい、『翁』からスタートして神様や女性を順番に演じていく能楽公演です。この順序にも理由があり、かつては太陽の動きに合わせ、その時間帯に一番適した曲を演じたのではないかと言われています。たとえば日があまり上がりきらない時間帯は神々しい神話の物語、女性が一番美しく見える最も日が高い時間帯は女性を扱ったもの、日が傾くと子を失う母の話など哀愁のもの、暗くなると鬼とか目に見えない幽玄なものといった具合です。自然と共存していた能楽の在り様が、今の時代も式能の形式に含まれていると言えるでしょう。僕自身も、一日の移り変わりに応じた曲目を提供するというのが能楽の醍醐味だと思っています。
和英さんは幼少時から能楽に携わっていらっしゃいます。そうしたお立場から、能楽の魅力とはどのようなところだと思われますか。
現在の舞台系のエンターテインメントはハリウッド式で、観客に激しい感情を起こさせることで嫌なことを忘れさせるといったスタイルが主流です。ただ、激しい感情は確かに活力にはなりますが、同時に自分自身の心を痛めることにもなりうるものです。たとえば、みんなで楽しくお祭りの時間を過ごすほど、ひとりの帰路は寂しくなりませんか? それはお祭りが楽しさだけでなく悲しさを作ってしまう要素になっているからです。一方、美術館に行っても、帰り道にそういうあまり感情は起こりませんよね。なぜなら美術館では、たとえば絵画を観ることを通して自分自身と対話する時間を作れるからです。絵画の鑑賞というのは、「今の仕事は本当に自分に合っているかな」など、絵画と関係ないことについても自分と話をゆっくりできる時間でもあるのだと思います。
そして能楽ですが、能楽はとてもゆったりしていて、時間がゆっくり流れます。これは絵を観ることと同様、能楽を観賞しながら自分と対話する時間をつくり出しているということです。特に自分の心に渦巻く「負」の感情を「まあまあ落ち着いて」と収める時間です。それゆえに、社会に出てさまざまな人間関係の中で生きている人ほど、能楽のゆったりと流れる時間を心地よく感じていただけると思いますし、それができる舞台芸術は能楽しかないと思っています。この能楽の価値は、どんなに時代が変わりエンターテインメントの傾向が変化しようが、ぶれてはいけないと思っています。
なぜ能楽の魅力が「観賞することで心を落ち着かせるところにある」と思われるようになったのですか。
僕は歌舞伎に対してライバル心を持っていて(笑)、だからこそ敬意を持って歌舞伎の魅力について真剣に考えました。そして、歌舞伎は人の心を動かして一緒に盛り上がる極上のエンターテインメントであるという結論にいたりました。ということは、能楽が同じことをやっても歌舞伎の後追いになってしまうので、歌舞伎とは異なる魅力を構築しなければいけません。ではそれは何だろうと考えた時、能楽は歌舞伎と対極で、静かに心を落ち着かせることができるじゃないかと気づいたのです。自分と真摯に向き合う時間を提供してお客様に寄り添うということも、現代社会において意義のあることなのではないかと感じています。

和英さんは古典的な能の上演のみならず、ご自身が主宰する「和の会」で人気声優による朗読能シアターの上演に取り組むなど、能楽を現代にひらいていく試みにも積極的に取り組まれています。こうしたご活動はどのような経緯で取り組まれるようになったのですか。
従来の能の公演と新たな試みは両輪だと思っていて、どちらも兼ね備えることがこれからの能楽のためにも必要だと思っています。ただし、重視しているのは650年続く根本的なものです。その片輪があることが前提となり、エンターテインメント志向というもう1つの車輪も動かせるのです。
今年は新たに「能楽カフェ」をやろうと思っています。実際にカフェを営業するわけではなくて、女性を対象に、現代の女性の抱えている問題や生活をよりよくするためのヒントを能楽から見つけて解決の道を探る、といったものです。能楽の魅力の話にもつながりますが、能を鑑賞する時に「理解しなくては」という強迫概念は捨てて、むしろ別なことをゆっくり、じっくり考える時間にして欲しいと思っていることから、このアイデアが浮かびました。
和英さんはイタリアを中心とする海外での事業にも力を入れられています。海外との文化交流を通して、ご自身の芸やご活動の上でのビジョンに何か影響はありましたか。
視野が広がりました。日本だけで活動していたら、お話したような能楽の魅力や価値に気づかなかったかもしれません。海外に出たことで、多くの人々が求めているものが能楽にあると肌で感じることができました。何万人も集めてというエンターテインメントの興行を基準としているのは日本とアメリカくらいじゃないかという気がします。イタリアなどでは人数よりも質を重視するので、その分薄利という課題がありますが(笑)。その辺のバランスを、お互いの国同士で勉強できたらいいなと思います。
イタリア公演は最初から「絶対にうける」という自信がありました。向こうでは今、禅がブームになっているので、江戸よりも室町のほうがフィットするだろうと読んでいたんです。また、これまでイタリアではほとんど『土蜘(つちぐも)』しかやってこなかったのですが、昨年のミラノトリエンナーレの公演では動きや音楽性、衣装などがイタリア人の琴線に触れるだろうと思った『乱(みだれ)』を上演することにしました。現地がちょうどバカンスシーズンだったので「人が集まらないからこの時期の開催はやめた方がいい」という意見もありましたが、ふたを開けてみればほぼ満席で、「なぜ1日しかやらないんだ」と言われたくらいです。
これからの能楽界を担うお一人として、抱負をお聞かせください。
僕の特徴は、すべてにおいて普通であることだと思っています。能楽師としての特別な能力や天性の何かがあると思っていませんし、経営者としても天性の感覚があるわけではなく、すべてにおいて同年代の人と同じです。ただ、そのすべてにおいて全力であろうとしている点は、自分のよさだと思っています。何事にも失敗を恐れず、逃げずにチャレンジするのが大事で、たとえ失敗してもしっかりそれを受け止めて次のステージに進むということを継続していけば、何かしらの実績を生み出していけるのではと思っています。
また、今後は能楽のビジネススキームの構築が僕の仕事だと考えています。伝統芸能という立場にあぐらをかくのではなく、いかに社会や経済において能楽の価値を作り出すかが重要です。「能楽をこのような方法で提供すると御社に対してよい影響が与えられると思います」など、はっきり言えるようなスキームを作り、そのビジネスモデルを能楽界で共有していきたいですね。
※ 能楽では演目のことを「曲目」と呼び、さらに曲のことを「番」と呼びます。曲の種類や「五番立て」という上演形式については、公益社団法人能楽協会ウェブサイトで紹介されています。
ページの内容終わり