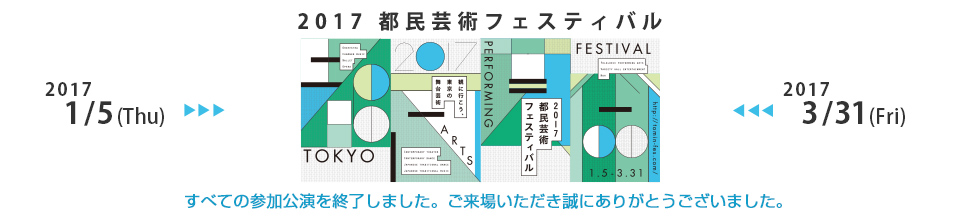2017都民芸術フェスティバル 公式サイト
今、演劇を上演するということ

渡辺 えり(わたなべ えり)さん
渡辺 えり(わたなべ えり)
山形県出身。舞台芸術学院、青俳演出部を経て、1978年から「劇団3○○」を20年間主宰。劇作家、演出家、女優として、また歌手として舞台、映像、マスコミのジャンルを問わず活躍する。
劇作家としては1983年『ゲゲゲのげ』で岸田國士戯曲賞、1987年『瞼の女 まだ見ぬ海からの手紙』で紀伊國屋演劇賞 個人賞、女優としては1996年『shall weダンス?』(周防正行監督)にて報知映画賞助演女優賞、日本アカデミー賞最優秀助演女優賞受賞など、数々の受賞歴がある。劇団3○○を前身とするおふぃす3○○によるオリジナルの舞台のほか、劇団外部での活躍も目覚ましい。劇団活動の傍ら「非戦を選ぶ演劇人の会」に参加。「反戦リーディング」という演劇人独特のアプローチで反戦を訴え続けている。
2006年に演劇私塾「渡辺流演劇塾」を開塾。可能性ある若い世代の育成に努めている。
今回の新作『鯨よ!私の手に乗れ』を上演されることになった経緯をお聞かせください。
タイトルにある「鯨」とは、私たちが夢見てきた理想を象徴したものです。そして、「夢を叶えたいと思ってずっと生きてきて、ようやくそれを叶えられそうな年代になった時には認知症になっていた」という人たちの希望の象徴でもあります。鯨は世界最大の動物種であるシロナガスクジラを想定しています。全長34mの、乱獲しすぎて今や絶滅種となってしまっている幻の鯨を、小さな頃から夢見たものの象徴として描きました。
今回この話を書こうと思ったきっかけはいくつかあります。まず、母が認知症になり介護施設に入所したという私自身の体験です。母の世代は青春を戦争に奪われ、戦後も歳をとるまで働きづめで、ずっと苦労してきました。子育てが終わって仕事も退職して、やっと自分の時間が持てるようになり、さあこれからはのんびり暮らしてもらいたいと思っていたところ、認知症になってしまって。料理も作れなくなってしまった母を見た時のショックは大きかったですし、ようやく自由に過ごして欲しいと思っていたのに、介護施設に入所し集団生活を余儀なくされている母を見るのもつらかった。自宅では自分のリズムで生活していた人が、毎日同じ時間に起きて同じ時間に食堂に集まって食事して、これまでショートカットなんかしたことなかったのに、髪の毛も短く刈られてしまって、まるで収容所で暮らしているようで。そうは言っても、施設もスタッフの皆さんも24時間体制でしっかりやってくださっているんです。弟夫婦もよかれと思って母を施設に入れたんです。けれど私には私の言い分があるわけで、これまで仲の良かった姉弟の関係まで悪くなったりと、まるで小説みたいなことも起こりました。この一連の出来事を芝居にできないだろうかと思ったのがまず1つのきっかけです。
次に、スペインのバンド・デシネ※1作家パコ・ロカ氏の原作をアニメーション化した『皺 Arrugas』を観たことです。これも認知症や介護施設をテーマにした話なんですが、認知症になった人が、自分のいる施設の部屋は急行列車で、ずっと旅をしていると思っているシーンにじーんと来ました。「そうだよな、認知症になっても夢を追いかけるってことはあるんだな」と。
それから劇団民藝の『八月の鯨』を観たことにも触発されました。老姉妹が暮らす別荘の前の入り江には、昔はよく鯨が訪れていて、めっきり姿を見せなくなってしまっても二人はまた鯨を見ることを夢見ています。そしてかつて好きだった男性が来訪してときめくんですが、その乙女心がとても美しいと思ったんですね。そして「鯨というのはいいな、しかも冬に夏の鯨を思っているという感覚がいいな」と思うと同時に、年老いたことを美しく描きたいという思いが生まれました。
そして、男社会の中で頑張って来た私たちが歳をとっていつか施設に入る日が来たら、そこでも演劇の好きな人が集まって芝居をやりたいと思ったことで、「認知症になろうが40年前にやりたかった芝居を亡くなる前にやろうと介護施設で練習している」という設定もいいんじゃないかなと考えました。こういった思いから生まれたのが今回の作品です。
渡辺さんはテレビや映画などでも幅広くご活躍されていますが、戯曲を書き、演出・振付をご担当され、生の舞台で演じる演劇とは、渡辺さんにとってどのようなものなのでしょうか。
私にとって演劇とは「自分の作りたいものを作れる」ものです。テレビや映画は「与えられた役を演じている自分」がいるという、いわば「仕事」であり、それは本来の自分とはまったく違う人間なわけです。確かにテレビや映画は観てくださる人も多いし反応も大きい、けれどそれなりにしがらみもあって、自分の思うものをそのまま表現できる世界ではありません。人間って、たとえお金にならなくても自分の好きなことをやりたいと思うじゃないですか。私にとってはそれが自ら作・演出する演劇なんです。残念ながらテレビや映画でファンになってくださった方は、なかなか劇場には来てくださらないんですよ。それは劇場での芝居がシュールだから、テレビや映画で見る私と違うからです。ストーリーがきわめてわかりやすい商業演劇の場合は何万人も足を運んでくださるのですが、劇団3〇〇での芝居は絵画で言えばルネ・マグリットの描く不可思議な絵のようなところがあるので、それを受け入れられる方、考えることが好きな方でないと足を運んでいただけません。それでもやりたい、身銭を切ってでもやりたいというのが私にとって演劇です。
よく「そんな金も手間もかかるもの、やめればいいじゃないですか」って言われるんですが、舞台での芝居をやめたら私の中のバランスが保てません。テレビや映画の仕事を頑張れるのは、自分のやりたいことをできる舞台があるからです。それに体制に対して言いたいことを私の意見として発言することは許されなくても、芝居の中では言えますしね。今回の作品は社会に対する問いかけもかなり入っているので、そこも思い切ってやりたいと思っています。いろいろな規制が入る時代だからこそ、演劇だけは自由にやりたいし、それをやれる場があることが、私の均衡を保ってくれているのです。
戯曲を書かれる際に心がけていらっしゃることなどはありますか。
人物を丁寧に扱うことですね。ストーリーを劇的にするという都合で人を殺すような芝居もありますが、決してそういうことはしません。やむにやまれぬ事情があって死んでしまう人がいるシーンの時は、本当にその人が実在していると思って、大事に書くことを心がけています。
今回の出演者の皆さんのご紹介をお願いします。
木野花さんは私と同じ頃に演劇を始められて、学校の美術の先生から転身されて劇団青い鳥を結成されました。また如月小春さん※2という方も同時期にいらして、木野花さんは演出のみでしたが、当時は女で作・演出をするって非常に珍しかったので、私も含めた3人は三羽烏と言われてよくマスコミに取り上げられました。最初は反目しあっていたんですよ(笑)、テリトリーが違うから。けれど40代になると同じ時代を共に苦労して道を切り開いてきた同性ということで親しくなっていったのですが如月さんが急逝され、木野花さんとふたりになってしまった。それでも3人で話していたとおり、いつか一緒になにかやろうねと話していました。それで2003年に『りぼん』という作品で木野花さんに出ていただいて、そして今回は木野花さんが演出する感じを想像し、登場人物をあて書きしました。
久野綾希子さんは劇団四季の『キャッツ』で歌っている姿を華やかな方だなと見ていました。それで『オールドリフレイン』という江戸糸あやつり人形結城座の作品で、唯一の人間の俳優として出ていただいたらとてもよかったんですよね。それで今回は、40年前はヒロインだったけれど今は認知症という役で出ていただいています。銀粉蝶さんは今回、体調不良で降板した田根楽子さんの代役で急きょ出演してくださることになりました。田根さんは私の母とも親しくて、私が山形に戻れない時も田根さんが泊まっていたくらいの仲なので、ぜひ母の役をやりたいと言ってくれていて、私も田根さんにあて書きして書いていました。それが出演できないということになり、急なお願いにも関わらず受けてくださったのが銀粉蝶さんです。ご自身も劇団ブリキの自発団で小劇場のヒロインをされて、そういう苦労も知っている方なので、快諾してくださいました。
広岡由里子さんは劇団東京乾電池の新人の女優さんの頃からのつきあいです。私の大好きな演技をなさる方で、『ゲゲゲのゲ』で一緒に共演したときもとても面白くて、今回は私の弟のお嫁さん役で出ていただきます。桑原裕子さんは劇団KAKUTAの作・演出で、さらに女優でと、私とまったく同じような立場の方です。40歳ですが還暦の役をやってもらう、けれどこれがまたすごく説得力があるんですよ。夫の土屋良太には私の弟の役をやってもらっています。実話なので、実際に私がしゃべった内容が芝居に全部入っていますから、それを知っているだけに泣けますよね。あとは渡辺流演劇塾の塾生や、オーディションで決定した歌って踊って楽器も演奏できるメンバーが出演します。
渡辺さんはご自身の故郷・山形でのご活動も大切にされています。さまざまなエンターテインメントにあふれた東京の演劇シーンを、どのように思われていますか。また演劇塾に参加されている若い俳優さんたちに、演劇を通して何を獲得してほしいと考えていらっしゃいますか。

山形で演劇をしたいですが、人口が少ないからお客さんが集まらない。演劇はお客さんがいなければやっていけませんから、なかなか芝居をやれるような状況じゃないんですね。今の日本って格差がすごいですよ。山田洋二監督の映画にあるような地方の劇団が活発だった時代や宮沢賢治の時代は、まだ地方に劇団がいっぱいあって、しかもテレビも映画館もないからお客さんが集まりました。もちろん、今も地方で劇団を主宰して頑張っている方は沢山いらっしゃいます。でも私の場合は、東京から山形に公演をしにきた劇団にあこがれ、やりたい舞台の作品が東京にあると考えました。様々な面で、山形で芝居をやることは難しいと思い、東京での上演を続けています。
渡辺流演劇塾で若手を育てるのは、新しい作品を作るためです。新しい作品には新しい人材が必要で、人を育てていかなければ作品も生み出せないんです。歳をとったら歳をとった人の役をやり、動ける人が動ける役をやらないと。古くからいる人だけで芝居を作ってたら、ずっと介護施設の芝居をやらなくちゃいけなくなっちゃいますよね(笑)。
今の若い人たちは連携プレーが苦手なので、演劇を通して連携することの楽しさを伝えたいと思っています。「人は一人では生きていけない」ということに、気がつかないように生かされているんですよね。パソコンやスマホがあれば誰と接することなくどこにも出かけることなく、引きこもったまま何でもできるから。でも「そうじゃないよ、一人で見る夕日よりみんなで見る夕日のほうがきれいだし楽しいよ」って伝えたいですね。それに一人では小さい力でも、みんなで集まれば大きいことができます。それが演劇の醍醐味であり面白さでもあります。そうでなかったら、生の舞台は疲れるのでやらないほうがいいですよ。でもそれが楽しくて面白いからやっているのであって、時代に逆行しているかもしれませんが、人間として生まれてきたからには、人と連携したほうが楽しいと思うんです。世代のギャップで、自分が正しいと思ったことが若い人になかなか伝わらないジレンマはありますが、人間である以上、これについてはあきらめてはいけないと思っています。
観客の方へのメッセージをお願いします。
自分の頭で考え、自分の目で観て欲しいですね。日本人は多数に飲まれやすいと思うんです。たとえば戦争反対だと思っていても自分以外がみんな戦争賛成だと言っていると、ついそっちに乗っかってしまうといった具合に。歴史を見てもそういう体質があるのがわかりますよね。けれどそれでは本当の目で物事が見られなくなるので、やはり自分の感覚を大事にしていただきたい。そうでないと芝居は楽しく観られませんし、概念にとらわれては面白くないんじゃないかなと思います。脳みそを自由にして、ご自身を生まれたばかりの赤ん坊だと思って、その状態で観ていただくと非常に面白い芝居だと思います。また、終演後のトークにも八嶋智人さん、松金よね子さん、市村正親さん、根岸季衣さん、永井愛さん、上田岳弘さんなど、日替わりで多彩な方々が登場してくださいますので、そちらもぜひ楽しんでいただければと思います。
※1 ベルギー・フランスを中心とした地域の漫画。
※2 如月小春さん(1956年-2000年)は渡辺えりさんと同じく1980年代の小劇場演劇を牽引した劇作家、演出家。
ページの内容終わり